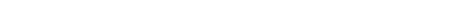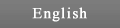胸部外科学
組織紹介



医学専攻 腫瘍制御医学系:胸部外科学講座の概要
詳しくは、当該 医学専攻 腫瘍制御医学系:胸部外科学講座 ホームページをご覧ください。
構成員の紹介
| 教授 | 今井 一博 | Kazuhiro IMAI |
|---|---|---|
| 講師・病院准教授 | 佐藤 雄亮 | Yusuke SATO |
| 講師・外来医長 | 高嶋 祉之具 | Shinogu TAKASHIMA |
| 講師 | 寺田 かおり | Kaori TERATA |
| 医学部講師 | 脇田 晃行 | Akiyuki WAKITA |
| 助教 | 高橋 絵梨子 | Eriko TAKAHASHI |
| 助教 | 松尾 翼 | Tsubasa MATSUO |
| 医学部助教・医局長 | 長岐 雄志 | Yushi NAGAKI |
| 助教 | 栗山 章司 | Shoji KURIYAMA |
| 医員 | 岩井 英頌 | Hidenobu IWAI |
| 医員 | 鈴木 陽香 | Haruka SUZUKI |
| 医員 | 山口 歩子 | Ayuko YAMAGUCHI |
| 医員 | 石井 良明 | Yoshiaki ISHII |
| 医員 | 米屋 崇峻 | Takatoshi YONEYA |
| 医員 | 今野 ひかり | Hikari KONNO |
| 医員 | 南塚 祐介 | Yusuke MINAMIZUKA |
| 医員 | 高橋 吏 | Tsukasa TAKAHASHI |
| 医員 | 森下 葵 | Aoi MORISHITA |
| 医員 | 加藤 圭亮 | Keisuke KATO |
| 事務系スタッフ | 小玉 純 | Jun KODAMA |
| 事務系スタッフ | 佐藤 祐美 | Masumi SATO |
| 研究系スタッフ | 若松 由貴 | Yuki WAKAMATSU |
| 医師事務クラーク | 原田 美香子 | Mikako HARADA |
| 医師事務クラーク | 中川 亜美 | Ami NAKAGAWA |
教育と研究の概要
主な担当授業
主な学部の授業
講義
3年次:呼吸器・食道・乳腺の構造と機能を理解し,主な呼吸器疾患の原因,病態生
理,症候,診断,治療を学ぶ
4年次:外科的治療と周術期管理,食事と輸液療法,医用機器と人工臓器,輸血と移
植の基本,基本的臨床手技の目的,方法,適応,禁忌,合併症を学ぶ.
実習
5年次:臨床実習,BSL 実際の患者さんを通じて問診,身体所見,検査所見,術前術後
管理を学ぶ
6年次:クリニカルクラークシップに基づく体験型学習,主治医の一員として問診,
カルテ記載,検査計画,診断,治療方針の決定を行う.
教科書:当科作成プリント
主な大学院の授業
呼吸器外科,食道外科,乳腺・内分泌外科,肺障害,外科侵襲,癌免疫.
主な研究対象
研究
各診療グループはそれぞれの診療・臨床にのっとった研究を行っている(各グループの項参照)が,全体のテーマとして以下の研究を行っている.
1.リンパ流を考慮した癌のリンパ節転移の基礎的臨床的研究
2.医工連携による温熱療法・化学療法の研究
4.バイオマーカーの探索とその臨床応用に関する研究
医学専攻 腫瘍制御医学系:胸部外科学講座の概要
I.講座の変遷と沿革
1972年4月に阿保七三郎先生が初代教授に就任して外科学第二講座が開講した.1976年9月に医学部附属病院が開設され,外科学第2講座は胸部外科,心臓血管外科および一般外科を主体とした診療体制で本格的にスタートした.1984年4月に阿部忠昭先生が心臓血管外科初代教授に昇任し,診療科として独立し後に講座に昇格した.以後は阿保教授の専門である食道外科を中心とした消化器外科をはじめ,肺縦隔外科,乳腺・甲状腺外科など幅広い分野での診療研究に従事してきた.当時の教室の研究テーマとしては,食道癌手術成績向上に関する研究を中心に,癌免疫療法,乳癌のリンパ節超音波診断法の研究,細胞周期に基づく癌化学療法の研究などと広範にわたり,外科学第2講座の特質である自由闊達な気風に満ちあふれていた.
阿保教授が1996年3月に定年退官した後,1997年2月に小川純一先生が第2代教授に就任した.小川教授の専門である呼吸器外科はもちろん,食道外科,乳腺・甲状腺外科の3専門領域の診療・研究を行っている.2002年4月に医学部の講座再編に伴い外科学講座呼吸器外科学分野に,そして2009年4月から医学部の大学院化に伴い医学系研究科医学専攻腫瘍制御医学系呼吸器・乳腺内分泌外科学講座に名称変更となったが,呼吸器外科,食道外科,乳腺・甲状腺外科の3専門領域の診療・研究を継続して行っている.また講座名は変更されたが,開講以来続いている自由闊達な気風は,良き伝統として脈々と受け継がれている.そして開講以来数多くの外科医を育成・輩出して,秋田県はもとより日本の医療に貢献してきた.
本学を卒業した初の外科学講座教授である南谷佳弘先生が,平成25年(2013年)5月から,第三代教授として胸部外科学講座に就任した.教室の基幹研究として,電界(非接触)撹拌技術を応用することにより,2時間以上を要する免疫組織化学染色を最短13分に短縮させる「迅速免疫組織化学染色装置・R-IHCラピート」を,南谷教授が中心となり開発を進めた.この研究は多くのメディアで話題となり,経済産業大臣賞を受賞している.南谷教授は,令和2年(2020年)から2期5年間,秋田大学医学部附属病院長を勤め上げ,令和6年(2024年)4月,国立大学法人秋田大学第十四代学長として,秋田大学に集う学生・教職員を含めた全ての秋田県民の舵取りを任された.
そして,令和7年(2025年)5月から,現教授である今井一博先生が昇任した.当教室では,食道癌・肺癌を含む肺腫瘍・縦隔腫瘍に対してロボット支援胸腔鏡下手術を行っている.今井教授は,秋田県において唯一人である,術者として基準を満たした技量を取得し,さらに他者によるロボット支援手術を円滑且つ安全に指導できる(プロクタリング)指導者(プロクター)として,後進の指導や県内関連病院への普及を推し進めている.新たに加わった重症筋無力症に対する剣状突起下アプローチ・ロボット手術も積極的に行っており,胸骨縦切開を回避した低侵襲かつ安全な手術を提供している.
教室史を彩る四教授は,アカデミック・サージャンとして,がん治療やその予防にも新たな道を切り開いた.万が一県内の手術数が減少しても,基本技術を磨く機会を失うことなく,「一例の経験で十例の価値を」をモットーに,育成の文化を定着させている.
II.現在の講座概要と研究状況
現在の講座スタッフの構成は教授以下,病院准教授1名,講師3名(医学部講師1名含む),助教4名(医学部助教1名含む),医員10名であり,そのほか社会人大学院生や関連病院への出向者などを合わせると100余名に及ぶ.現在の当講座における診療・研究の目標は,癌の悪性度や転移形式,術後の病態生理などを解明し,それぞれの患者さんに最も適切な治療法を行うことであり,それにより予後の改善とQOLの向上が得られると考えている.
1.呼吸器グループ
診療内容:
肺癌や転移性肺腫瘍などの腫瘍性疾患の外科治療を中心とした診療を行っている.早期肺癌にはダヴィンチサージカルシステムを用いたロボット支援胸腔鏡下肺葉切除を行っている.新たに加わった重症筋無力症に対する剣状突起下アプローチ・ロボット手術も積極的に行っており胸骨縦切開を回避した低侵襲かつ安全な手術を提供している.また2cm以下の末梢小型非小細胞肺癌に対しては根治性を落とさずに肺機能を温存できる区域切除を積極的に導入している.また進行した肺癌や縦隔腫瘍に対しても気管気管支再建を伴う手術等で根治性を落とさずに機能を温存する手術を積極的に取り入れている.他の病院では手術が難しい肺癌や縦隔腫瘍の症例も数多く集まっており,秋田県の呼吸器外科の中心的な施設として機能している. 肺癌を中心とした胸部悪性腫瘍は呼吸器内科,放射線科,病理医,呼吸器外科で構成される肺癌キャンサーボードで治療方針の決定を行っている.
研究内容:
・合併症ゼロを目指した個別化医療技術の開発
・電界撹拌技術を応用した迅速免疫組織化学染色診断
・電界撹拌技術による術中迅速・Spatial Transcriptome Mapping
・細胞系譜解析マウスを用いた腫瘍免疫環境の動的理解
・殺細胞性化学療法・免疫チェックポイント阻害薬併用療法における免疫細胞ダイナミクス
・血液製剤を使用しない確実な肺瘻閉鎖を実現するガロール基高強度水中接着シートの開発
2.食道グループ
診療内容:
主に食道癌の外科治療を中心とした診療を行っており、食道癌手術症例数は教室発足時から総計1,700例を超えた.食道癌治療方針は食道外科医,消化器内科医,臨床腫瘍内科医,放射線科医から構成される食道癌キャンサーボードで決定している.病期I食道癌患者には術前治療なしで胸腔鏡下手術あるいはロボット支援手術を行っている.病期II-III食道癌患者には術前治療(術前化学療法・化学放射線療法)を行った後で同様の手術を行っている.根治的化学放射線療法後の再燃症例には積極的な救済手術(サルベージ手術)を行っている.免疫チェックポイント阻害薬での治療経験も豊富である.その他,食道アカラシア,逆流性食道炎,食道裂孔ヘルニア,食道良性腫瘍などに対する鏡視下手術も行っている.下記のとおり臨床に直結する研究を複数行っており、これまで以上に合併症が少ない食道癌手術を行えるようになってきている。
研究内容:
・高接着強度の水中接着剤を応用した生体用接着シートの開発(東京大学,グンゼ株式会社との共同研究)
「令和7年度AMED次世代ヘルステック・スタートアップ育成支援事業」採択
特願 2024-160040 (2024 年 9 月 17 日) 発明者:佐藤 雄亮、江島 広貴
・食道癌患者の口腔内環境が不良なことから口腔内の歯周病菌と善玉菌が食道癌に及ぼす影響
・口腔内の歯周病菌と善玉菌が食道癌に及ぼす影響におけるToll-like receptorの役割
・L8020乳酸菌が産生する特定のペプチドの癌細胞増殖抑制効果
特願 2025-008744 (2025 年 1 月 21 日) 発明者:佐藤 雄亮、二川 浩樹、利光 勝久、坂田 真理
・L8020乳酸菌入りオーラルケア商品が食道癌術後の合併症発生率を下げるのかという特定臨床研究 jRCTs021230010(広島大学,ジェクス株式会社との共同研究)
・L8020乳酸菌入りオーラルケア商品が口腔内に発生する発癌性物質アセトアルデヒドを減少させるのか
という特定臨床研究の準備中(米国スタンフォード大学,台湾高雄大学,ジェクス株式会社との研究)
・L8020乳酸菌入りオーラルケア商品が2型糖尿病患者の血糖コントロールを改善するのか
という特定臨床研究の準備中(秋田大学糖尿病内分泌内科,ジェクス株式会社との共同研究)
・L8020乳酸菌入りオーラルケア商品が認知症患者の症状を改善するのかという特定臨床研究の準備中
(秋田大学高齢者医療先端研究センター,ジェクス株式会社との共同研究)
・頚椎サポート装具の開発(秋田大学理工学部との共同研究)
特願 2023-014058 (2023 年 2 月 1 日) 発明者:佐藤 雄亮、趙 旭、高橋 朗人、村岡 幹夫
・食道癌における新規放射線感受性制御の探索
-MAPKシグナル経路操作による新規放射線感受性増強剤の開発
-高精度遺伝子解析および遺伝子編集技術を用いた放射線感受性中心因子の検索
-腸内細菌叢変化によるToll-like receptorを介した食道癌新規放射線感受性制御
・免疫チェックポイント阻害薬の効果予測
-免疫チェックポイント阻害薬の至適血中濃度の確立
-免疫チェックポイント阻害剤の治療効果予測マーカーの同定
・食道扁平上皮癌におけるエピトランスクリプトーム制御によるリンパ節転移治療法の開発
3.乳腺内分泌グループ
診療内容:
対象は乳腺,甲状腺,上皮小体疾患である.乳癌の治療に関しては放射線科との協力により、MR I撮像法を新たに開発し、より感度の高い画像の作成に成功している。更にこの技法を拡がり診断にも応用し、より詳細な拡がり診断を行うことにより必要かつ十分で最適な切除範囲を決定し,美容にも十分な配慮した低侵襲な乳房温存療法を行っている.更に、当教室で開発した迅速免疫染色法の活用により、術中に精緻な病理診断を可能としている。更に迅速免疫染色と人工知能(AI)診断の融合により、迅速で精緻な労働力にも貢献する病理診断システムの開発に向けて多施設共同研究に取り組んでいる。秋田大学理工学部との共同研究により、ICP-MSを用いた血清及び癌組織中の微量元素との関連についての研究にも取り組んでいる。また、腋窩郭清は術後のリンパ浮腫、生活の質(QOL)の低下につながる合併症であるため、これを軽減すべく腋窩縮小手術の確立に向けた多施設共同臨床試験に取り組むとともに、新規治療開発にかかわる各種臨床試験、治験参加施設となっている。
研究内容:
・術前画像診断:特にMRIによる拡がり診断
・迅速免疫染色法の活用(センチネルリンパ節診断、乳房部分切除断端診断)
・迅速免疫染色とAI診断による迅速で精緻な病理診断システムの開発
・乳癌患者の血清微量元素濃度及び乳癌組織内の血清微量元素について
・腋窩縮小手術の開発
・臨床試験、治験への参加