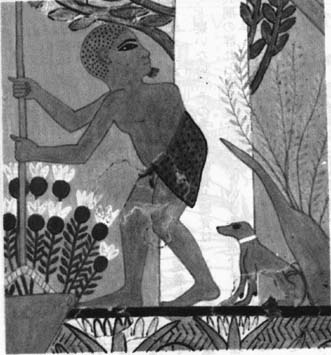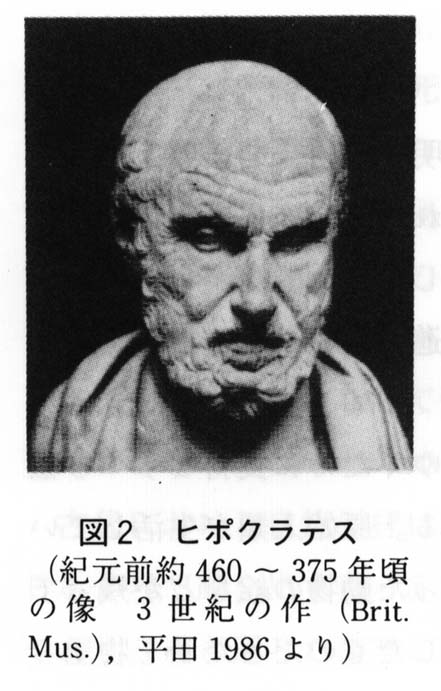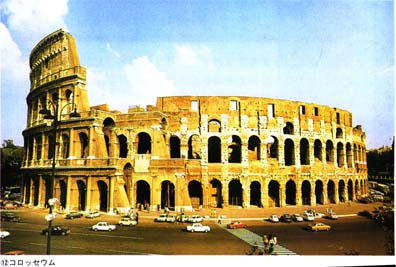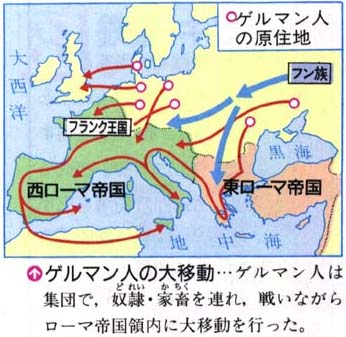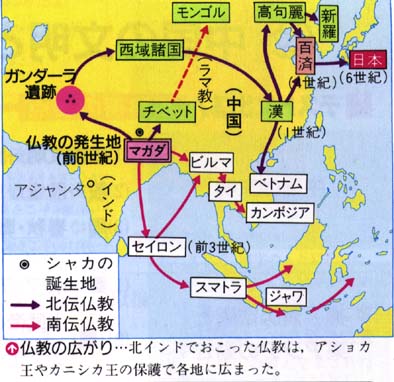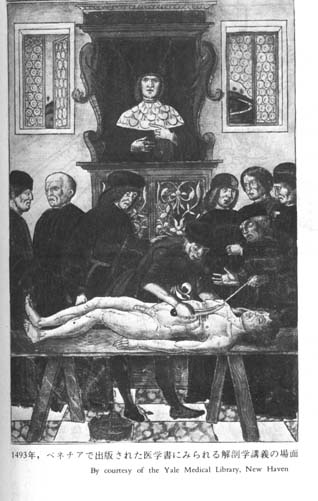人類は100万年程の間は狩猟生活をしていました。右の図はラスコーの壁画ですが、数10万年続いた旧石器時代の終わり頃、今から2万年程前に描かれたとされています。この壁画には動物の中でも危険な種類のものだけが描かれています。それらの動物は当時の原始人にとっては大切な食料となるものですが、生命を脅かす恐ろしい存在でもありました。したがって、それらの動物に対して畏敬の念を抱いていたようです。アイヌの人々が山の恵としてクマを捕らえ、死んだクマを神として祭ることに通ずる考えのようです。
当時は小動物も沢山食べられていたことが洞窟の床のごみから判明しています。しかし、そのような小動物は壁画に描かれていないことから、このころの人類は大型動物に対してだけ畏敬の念をもち、動物の生命全般に対する畏敬の念は持ちあわせていなかったものと思われています。

ラスコーの壁画