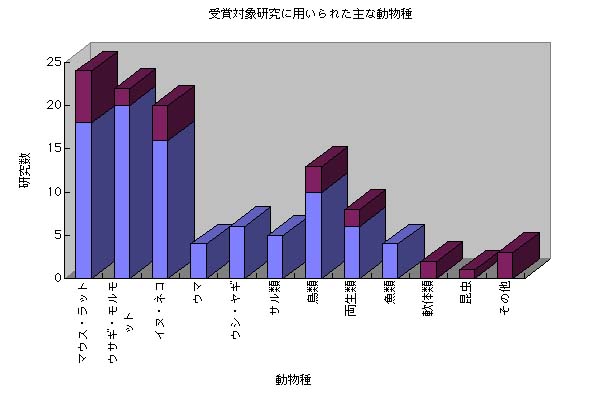イギリス以外では、クロード・ベルナールが1865年に実験医学序説を表しています。彼は注意深い計画の基に研究を行うフランスの生理学者でしたが、無麻酔でイヌの実験を行っていたことに心を痛めていた彼の妻と娘は、ベルナールの死後、動物実験反対運動に身を置くことになります。

ベルナールと弟子たち
|
18世紀後半の産業革命をステップボードとして19世紀は科学が発展し、科学の世紀といわれるほどになります。医学においても19世紀直前の1798年にジェンナーが牛痘をもとに天然痘の治療を確立しました。19世紀前半のイギリスではナポレオン戦争に勝利し、その後植民地を拡大して、ビクトリア女王時代には大英帝国として繁栄します。このころ1859年にダウインがビーグル号でガラパゴス諸島などを航海し、「種の起源」を表しています。 イギリス以外では、クロード・ベルナールが1865年に実験医学序説を表しています。彼は注意深い計画の基に研究を行うフランスの生理学者でしたが、無麻酔でイヌの実験を行っていたことに心を痛めていた彼の妻と娘は、ベルナールの死後、動物実験反対運動に身を置くことになります。 |
 ベルナールと弟子たち |
|
|