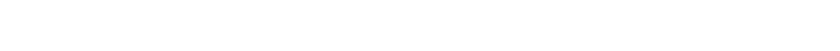- トップページ
- 診療案内
- 検査・治療/疾患情報
- 腎腫瘍
腎腫瘍とは
腎腫瘍について
秋田大学医学部泌尿器科 講師 堀川洋平
腎腫瘍とは
腎臓にできる腫瘍の大半は悪性で腎がんと呼ばれます。中でも腎尿細管上皮細胞(皮質近位尿細管)由来の腎細胞がんが大部分を占め、発生頻度は人口10万人あたり2.5人程度です。男女比は約3:1で男性に多い傾向があります。
組織学的には6種類に分けられ、VHL遺伝子などの遺伝子異常により家系内発生が見られるものもあります。他の腎がんとしては、極めて稀ではありますが、若年に多く(27~54歳)悪性度が高い髄質集合管由来のベリニ管癌や特殊な腎がんとして長期透析患者に見られ後天性嚢胞腎に発生する透析腎がんが知られています。
良性腫瘍としては腎血管筋脂肪腫が最も知られており、他に乳頭状/管状乳頭状腺腫、オンコサイトーマ、後腎性腺腫などがあります。
腎がんはほぼすべてが治療の対象となりますが、良性腫瘍もがんとの鑑別が困難であったり、大きくなり(10cm以上)自然破裂の危険性がある場合には手術適応になることもあります。
腎腫瘍の症状
腫瘍が大きくなるにつれ血尿(40%)、疼痛(15%)、腹部腫瘤触知(5%)などがみられ、急速に進行する場合には発熱、体重減少などを伴うこともあります。ただし5cm以下の小さい腫瘍では症状を伴わない場合も少なくなく(27%)、検診や人間ドックで偶然見つかる機会が増えつつあります。
腎腫瘍の診断
超音波検査は検診、人間ドック、泌尿器科外来などで最初に行われることが多い検査で、患者様の負担が少なく、良性疾患との鑑別も大部分で可能であるなど診断学的価値も高い検査です。
この検査において腎内や腎外に突出する腫瘤が認められなど、腎腫瘍を否定できない場合さらにCT検査が施行されます。この検査により腎がんと他の疾患との鑑別診断はもちろん、腫瘍の広がりやリンパ節転移の有無などを知ることが可能です。
腎臓にできる悪性疾患で腎がんとは別に腎臓の中の尿路にできる腎盂(じんう)腫瘍がありますが、腎がんの一部は腎盂腫瘍との鑑別が難しい場合もあり、尿路を撮影するDIP(点滴静注腎盂造影)も行われることが多い検査です。MRIはCTで悪性疾患との鑑別が難しい場合に追加で行うことがあります。以前に広く行われた血管造影検査はMRIやCTで代用が可能になってきたことや、患者様への負担が大きいことなどを理由に、先の三つの検査で判断が難しい場合にのみ当科では行っています。
腎腫瘍の病期
腎がんの進展度(病気の進み具合)は原発腫瘍(T)、所属リンパ節(N)、遠隔転移(M)のTNM分類が用いられ、これをもとに四つの病期分けられます。この病期により患者様の治療方針や治療後の経過に大きな差があるため、手術前、手術後の正確な病期を決定することは非常に重要です。
TNM分類
- T-原発腫瘍
- T1 最大径が7cm以下で、腎に限局する腫瘍
- T2 最大径が7cmを超え、腎に限局する腫瘍
- T3 腫瘍は主静脈内に進展、または副腎に浸潤、または腎周囲に浸潤するがGerota筋膜を越えない
- T4 腫瘍はGerota筋膜を越えて浸潤する
- N-所属リンパ節
- N0 所属リンパ節転移なし
- N1 1個の所属リンパ節転移
- N3 2個以上の所属リンパ節転移
- M-遠隔転移
- M0 遠隔転移なし
- M1 遠隔転移あり
病期分類(I、II、III、IV)
| I期 | T1 | N0 | M0 |
|---|---|---|---|
| II期 | T2 | N0 | M0 |
| III期 | T1 | N1 | M0 |
| T2 | N1 | M0 | |
| T3 | N0,N1 | M0 | |
| IV期 | T4 | ||
| Tに関係なく | N2 | ||
| TNに関係なく | M1 |
腎腫瘍の治療
(1) 手術療法
病気の完治を目指す場合、現在手術以上のものはありません。当科においても腎癌の患者様には手術を第一にお勧めしています。
手術には大きく開腹手術(根治的腎摘除術、根治的腎摘除術+下大静脈内腫瘍血栓除去術、腎部分切除術など)、腹腔鏡手術(腹腔鏡下腎摘除術、後腹膜鏡下腎摘除術、腹腔鏡下腎部分摘除術など)の二つがあり、腫瘍の大きさ、伸展度、患者様の体力、腎機能、患者様の希望などにより手術方法を検討します。
最近は患者様の術後の回復が早い、腹腔鏡下手術を選択する機会が増えつつあり、秋田大学では腫瘍のサイズが8~10cm以下であればほとんどの例で腹腔鏡下手術で行っています。腹腔鏡下手術の難点は術者の熟練が必要なことですが、幸い当科では、腹腔鏡下手術普及の初期より経験してきており、現在年間40件程度の同手術を行っています。
(2) 免疫療法
転移が手術前より認められたり、摘出臓器の病理学検査結果により進行腎がんと診断された患者様には、手術後にインターフェロン‐α(INF‐α)、インターロイキン‐2(IL-2)などの薬剤投与による免疫療法が行っています。
具体的には病期III以上やT2で静脈にがんが進行 しているような場合がこれにあたります。
INF‐αの効果は、著効率(4週以上完全消失)2~7%、有効率(50%以上縮小が4週以上持続)が12~18%と報告されています。
IL-2は1999年に本邦でも腎がんに保険適応となった比較的新しい薬です。効果発現まで3か月を有し奏功率は15%とされています。
INF‐α、IL-2などの薬品は、使用量・投与方法についても一致した見解はなく、連日投与、週1回投与、隔週投与などさまざまであり、奏功率も10~20%と決して高いものではありません。
ただし、5年生存率を比較すると、腎摘除のみ12.5%、免疫療法のみ0%、腎摘除+免疫療法20%と若干の差が報告されており、効果を期待して使用しているのが現状です。
(3) 抗癌剤による化学療法
抗癌剤による化学療法は転移や手術後の再発などに用いられることがありますが、腎がんには抗癌剤の効果はあまりないと考えられてきており、慎重に選択すべき治療法です。
海外で行われた腎がんに対する抗がん剤治療の大規模調査において奏功率は6%にすぎず、ある程度の効果は期待できる薬剤として5-FU(5%)、ビンブラスチン(7~9%)、Ifosfamide(6%)、Gemcitabine(7%)が挙げられている程度です。
副作用の出現を考慮した場合、その効果は免疫療法と比較しても満足できるものではありません。INF、IL-2の併用、INFと抗がん剤の多剤併用療法は、単独投与に比べ併用療法はやや効果があるようですが、いずれもINF単独療法を凌駕する明確な報告はありません。副作用・予後等含め、総合的な判断で併用療法が有効であるかは今後の検討課題です。
また抗癌剤と免疫療法を組み合わせた治療法についても秋田大学で検討中です。
腎腫瘍の予後
2001年の報告では腫瘍分類(TNM)に基づいた病期分類(I~IV)で分けた腎癌手術後の全体の5年生存率は、
- 病期I:95%
- 病期II:88%
- 病期III:63%
- 病期IV:23%
とされており、秋田大学の成績もほぼ同程度です。
手術後の再発は、病期Iや病期IIでは10%以下ですが、病期III以上では約40~50%に認められ、再発好発部位は
- 肺46.7%
- 骨17.8%
- 後腹膜臓器11.1%
- 肝6.7%
- 甲状腺4.4%
- 脳2.2%
などが多いとされます。
摘出した臓器の腫瘍分類別再発率は、
- pT1:9.0%
- pT2:32.4%
- pT3:37.2%
と腫瘍が増大するにつれ再発率が高い傾向があります。
腎部分切除においては適応、根治性について現在も議論のあるところであるりますが、T1a、4cm以下Stage1に限局した場合、5年生存率98%と良好な結果が報告されており、当科でも4cm以下の腎癌に対して部分切除を20例以上に行っていますが、再発例はありません。
また腫瘍の位置によっては腹腔鏡などの内視鏡下にも部分切除は可能となっています。再発後3年生存率は10%以下と極めて不良であるため、再発の有無が患者様の予後を大きく左右すると考えられます。