トルコ感染症対策
元チームリーダー兼
感染症サーベイランス専門家 森田 盛大 |
 |
トルコ感染症対策
元チームリーダー兼
感染症サーベイランス専門家 森田 盛大 |
 |

中央奥の緑地帯にRSHCがある。 |

|

|

|

|



|

左端は宮村専門家 |
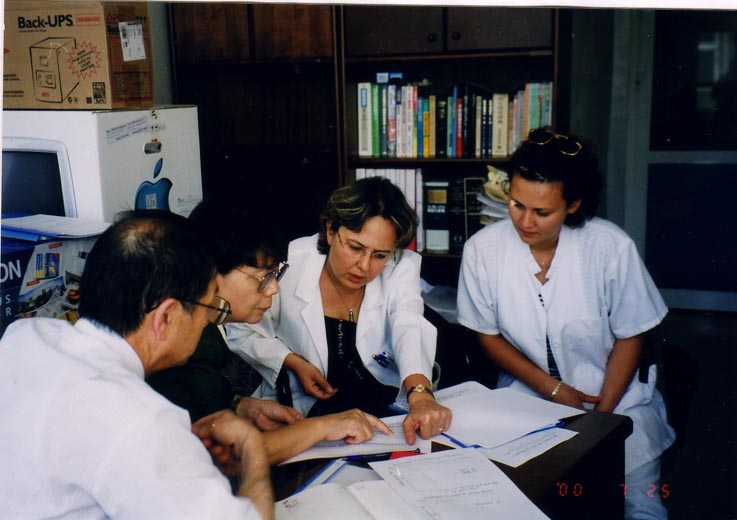
|
