|
学会には約40カ国、約700名の人が参加していました。最も参加者が多かったのは英国(128名)、次いで米国(103名)、開催国のイタリア(96名)、ドイツ(85名)、オランダ(47名)、フランス(41名)、日本(26名)の順。EC統合があるためかベルギー(26名)、スイス(25名)、スェーデン(18名)、デンマーク(17名)、スペイン(17名)の他チェコ、ルーマニア、アイルランド等20を越えるヨーロッパ諸国と若干の東欧諸国が参加していました。日本からは大阪大学の黒澤先生はじめ大学や化粧品メーカー関係の方が出席されました。 参加者の顔触れは動物実験代替法の研究者、動物実験関係者(動物実験を監督する立場の人も含まれる)、動物保護団体の関係者等のようでした。会場の入り口付近ではNo Vivisectionのプラカードを持った10人前後の動物実験反対者が地元警察の警戒する中、静かな抗議行動をとっていました。また、会場内にある諸団体用宣伝物配布コーナーには日本の実験動物愛護団体のビラも置かれ、それには「動物の法律を考える連絡会」が自民党に提出した法規制に関する要望書と小渕首相宛に日本の法律を改正するよう抗議を促す内容が英文で書かれていました。 |  |
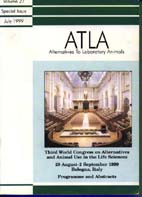 |
学会では代替法の開発や評価、データベース、3Rs、教育、倫理等A〜Eの5つのテーマが毎日並行して発表されましたが、我々は動物実験を規制している法律あるいは動物福祉の話を中心に聞いて参りました。 動物実験を規制する法律にかかわるセッションではオランダが中心となりセッションを仕切っていました。またニュージーランド、オーストラリアも近年基準が整備されたためか積極的な発言が目立ちました。米国と英国はそれらの発言を静観しているように見受けられました。ドイツに関しては代替法のテーマでは多くの研究者が発言しておりましたが、法律に関する紹介は殆どありませんでした。オランダのMinistry of Public Health, Welfare & SportのGeneral InspectorateであるPual de Greeveと話す機会を得ましたが、彼はオランダにいる900人?のinspectorの長だそうです。オランダにおける動物実験の法規制に関する状況については後日メールで尋ねることを約束しました。また、ドイツの法規制に関してはZEBET BgVVのBarbara Grune博士から状況が聞けそうです。 次回は3年後にボストンで行われますが、先進諸外国に比べて我が国の動物実験関係者の参加が少ないという意見も聞かれました。第4回世界動物実験代替法学会には実験動物学会会員あるいは動物実験施設の管理に携わっている方々も参加されることを期待します。 |
The Use of Cats and Dogs as Laboratory Animals
Should cats and dogs be used as laboratory animals?
イヌ、ネコは生物医学の研究において世界中で使われている。それらの動物を使う目的には化学物質の毒性試験、基礎的研究、ヒトや動物のワクチンの開発、解剖や外科的手技の教育も含まれる。英国ではAnimals (Scientific Procedures) Act 1986により動物実験計画を許可する前に、研究計画のcosts and benefitsを検討することを要求されている。さらにイヌ、ネコを含むある種の動物を実験に使うに当たっては代替動物がないあるいは入手困難であることを示す正当な補足説明(additional justification)が要求される。このような法規制があるにもかかわらず、英国で1997年に行われたイヌを用いた実験は7,490件、ネコを用いた実験は1,446件であった。世界中では何千もの実験が行われていた。英国でイヌ、ネコを使用するに当たって補足説明(additional justification)を要求する根拠は明らかではないが、これらの種はコンパニオンアニマルとしての地位にあるがゆえに、特別に保護されているらしい。
オーストラリアでは、研究、教育、試験での動物の使用はAustralian Code of Practice for the Care and Use of Animals for Scientific Purpose, 1997によって規制されている。特に、この基準では動物実験に当たっては実験目的に適した動物種を選択するよう要求している。
オーストラリアでは、動物実験に使われるイヌとネコは大変わずかでしかないが、それでもこの問題に関しては多くの議論がある。
このワークショップではコンパニオンアニマルの動物実験使用に関して賛成、反対の立場から議論されることとなると思う。また、イヌ、ネコの使用にかかわる倫理的、実際的問題も提起されるであろう。議論の焦点は、もしイヌ、ネコに代る代替動物がいるとしたら、イヌ、ネコを実験に使うべきではないとする合理的な根拠を明らかにすることにある。
(原文)
|
以下は、このワークショップを聞いての私の感想です。 イヌ、ネコの使用について賛成(オーストラリアの女性)と反対(米国の女性)の立場から意見が展開された。フロアーからも意見が出されたが、使ってもよいとする科学的根拠に基づく意見と使ってはならないとする感情的意見が平行線をたどり結論は出なかった。 フロアーのドイツの方からイヌはだめであるがブタなら多いに使いなさいという意見が出され、国(個人かもしれませんが)によって動物種に対する考え方に違いがあることが確認され興味深かった。 また、オーストラリアでは、野生化したイヌやネコがオーストラリア固有の野生動物を侵害しているということでイヌ、ネコに対しては英米に比べ好感を持っていないように感じた。 |  |